放射線被曝管理方策の改革提案
加藤和明
2016年06月04日 |
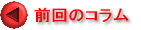 |
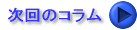 |
先ずは、改革の必要性を述べるべきであろうが、書き出すと多くの字数を要すること必定なので、ここでは省略する。 何れ、どこかの場を借りて、縷々書き留めたいと願って居るが、断片的には長年に亘って指摘してきたことである。
放射線防護の対象や手段に使われる科学・技術の発展は日進月歩であり、また、安全や安全確保に係る個人や社会の考え方も時の流れに従って変化していく。
安全確保のための対策は、言ってみるなら、当事者と社会との契約、として決められることである。 しかしながら、契約を合理的に締結するために不可欠な“安全の哲学や理念”は確立されず、“安全確保の目標設定や手法の確立”に社会の合意が得られていないのが現状である。
5年前に起きた福島原発の事故により、我が国の放射線防護に係る制度設計は、根幹から見直しを行い、一刻も早く再構築を図るべきと訴えてきた。 しかしながら、そのような“動き”は仲々目に留まらないのが残念である。
5年前、当時考えたことをこのコラムに書かせて戴いた(2011/10/11:放射線防護に係る国の制度設計再構築の提案)が、その後も自分なりに検討を続けてきたので、改めて、現在の自分の考えを述べてみたいと思うに至った。
ともあれ、放射線防護システムの再構築に当っては、以下に掲げる事項への配慮が望ましいと考える。
- “防護”を「人の健康に対する障害(望ましくない影響)発生の防止」に限定することが適切とは言えない時代となって来た。 ペットや家畜など動物やロボットも、放射線への被曝により、病気(機能喪失)になったり落命したりする。
高度の制御機能を組み込まれた無機の物質系や“エントロピーが増大する系”であるという意味で広義の生命体に含めてもよいと考える(都市や会社などの)組織をも対象とすることができるように、システの構築には汎用性(と同時に安定性)を備えることが求められる。
- 放射線とのつきあいは、(非平和利用であれ、平和利用であれ)原子力との付き合いを仮に止めたとしても、避けることができないものである。 それ故、現行の制度設計が原子力平和利用に係る法体系の中に組み込まれているのを改め、適応の領域拡大をより容易なものとすべきである。
放射線安全の確保に係る制度設計は、“核の傘の下”ではなく、より高位の“安全基本法”を制定し、その体系に組み込むことが望ましいと考える。
- 医学における診療に付随する放射線防護の方策を特別扱いすることは廃止すべき時期に来ており、また大量の放射線被曝によって発症した急性放射線症の診断・治療に特化した
dosimetryの開発も必要である。
放射線防護に係る制度設計の変更は、先述の理由で避けがたいことと認識するが、日頃慣れ親しんでいるものに“急激な変化”を与えることは、弊害も大きくなる恐れがあり、望ましいことではないと考えるので、改革は段階的に、少なくとも2段階で、進めることが望ましいと考える。
先ず、現時点で最も望ましいと考える究極の改革案について述べる。
- 「計量なくして管理なし」の原点に返り、計量されるべき量を本来の“放射線の量”である「粒子フルエンス」に求め、普遍性と安定性と測定に係る技術的可能性に優れた“加重フルエンス”を創出して「基本線量」と称えたい。
現行の放射線防護システムは、他本立ての“dose-effect relation”を持ち込み、それぞれに、基本線量、加重係数、被曝線量の管理基準という
3つの操作対象を持つので、自由度が余分となって居る。 基本線量には普遍性と安定性と望む限りの品質で直接測定評価が可能である量を採用すべきである。
筆者の提案は『標準物質系の定点における“水分子の電離確率”』を基本線量とすることである。 標準物質系には“直径 10cmの球体水”を取り、その中心を定点とすることが具体的構想である。
空間におかれた 1個の水分子を考える方が、放射線と線量の関わりがすっきりして分かりやすくなるが、物質系で起きる実際の電離は、放射線が物質系に作用して生成される電離性荷電粒子によってもたらされるものが主体であることを重視せざるを得ない事情がある。
120年前の黎明期には、線量として“空気の電離能”が使われていたが、その意義には軽視できないものがあると考える。 計量・計測の対象として“電気量”に勝る物理量は存在しない。
- 放射線管理システムの構築は、放射線防護学者の仕事である。一般的には、放射線場の関数である“粒子束フルエンス”と、同じく放射線場の関数である“防護加重係数”の
convolutionとして定義される「防護線量」を用いて行うが、その際には、放射線場の強度に係る時間的変動は粒子束密度にのみ負わせ、“場の性質は、線量評価に係る情報汲み出しの間、不変である”と仮定する。
Dosimetryとは「放射線の場に働きかけを行って得られる情報を“しかるべく情報処理”して値を評価する技術」であり、典型的な逆問題でもある。
場の強度とスペクトルで時間変数を分離できなければ問題は解くことが叶わないのである。 ここで、“防護加重係数”とは、単位フルエンスが与える防護線量を意味する。
- 防護線量は、防護の目的や対象などの違いに応じて適切に導入されて然るべきものと考え、導入に制限を設けないこととするが、それぞれに対し、導入の意図と適用領域を明確に示すことを求める。
- 放射線防護の現場においては、基本線量を計量の対象に据え、国なり専門機関なりによって提供もしくは推奨される荷重係数をこれに乗じて管理の対象量とする。
荷重係数は各種防護線量と基本線量の比として最適と判断されるものである。 “管理の対象量”を「管理線量」と呼ぶことにするが、それは、数学的にはスカラー量であり、空間的擬微分量である。
またその時間微分(管理線量率)や時間積分(管理線量)は“場の量”となる。 ただし、線量の時間微分で定義される線量率が時間的に変動する場合、そのスペクトルを実験的に求めることには、原理的にして技術的な困難が付随するので、放射線防護の管理手段としては一定の時間当たりの応答で定義される「時間線量」を使用するべきである。
- 管理線量の評価に“加算性の保証”は求めない。 これは LNTモデルに立脚したシステム構築の放棄を意味する。 ICRPがシステム構築に当たって使用を続けてきた“放射線被曝の
specific risk、すなわち、単位線量あたりのリスク、のデータは、広島・長崎に投下された原爆の性能評価のために行われた研究の成果に基づいており、他によく例を見る如く、“目的
orientedのバイアス”が掛かっている可能性がある。 核抑止力を強調したいという思惑もそれを助成してきた可能性がある。 また、原子力の非平和利用に係る記憶が鮮明に残る中で“平和利用”を開始したことから、それに付随する“放射線被曝”についてのリスク管理は、他のリスク要因に対するものと比較して突出して厳しいものとされるに至った。
そのため、古来の“立法”で、当然の指導原理とされていた“デ・ミニミス”(ラテン語 de minimis non curat praetor:法律は些事にかかわらず)は、どこかに捨てられてしまうところとなって居る。
次に、過渡期における、さしあたっての改革案を述べる。
- 現行の ICRP放射線防護体系で使用されている、等価線量と実効線量を“防護線量”と呼び、現行の国の制度設計で測定対象量に指定されている線量当量を(4.で述べた)「管理線量」として使用する。
- 管理線量の測定・評価に際しては、(従来の“追加線量”の考えを排し)放射線の出自や被曝の由来などによる選択制限を設けない。
- “被曝線量”の測定・評価は、測定の基準時間を 1時間および 1日と定めて行うこととし、それぞれを「時間線量」「日線量」と呼ぶ。
- 被曝線量には内部被曝によるものを含めない。 内部被曝の管理は放射性物質の摂取管理に依ることとし、外部被曝管理と切り離す。
- 「時間線量」の測定・評価の結果が 1mSv以下であったときには、その事実を、可及的速やかに、当人に知らせることを義務付けるが、それ以外の事後行為は求めない。
この測定は当人及び関係者に“安心”を与えることを目的とするものであり、必要に応じ「1mSv以下の放射線被曝ではリスクの量はゼロと見做せる」という見解の説明を行うことが推奨される。
- 「日線量」の測定・評価の結果が 10mSv以下であったときにも、前項同様、その事実を、可及的速やかに、当人に知らせるとともに、管理の任にある者がその事実を記帳し、一定期間保管するものとする。
- 「時間線量」の測定・評価が 1mSv、「日線量」のそれが 10mSvを超えたときには、放射線取扱主任者の国家資格を有する者に被曝の詳細についての調査を、また医学界が専門医と認める者による健康診断を依頼する仕組みを、国としての制度設計として整えるものとする。
- 「日線量」の測定・評価を行った日の数が、年度内に 100を超えたときには、居住地の保健所に届け出、指導を受けるものとする。
- 個人のリスクに関わる管理は、基本的に当人の裁量に委ねられるものとするが、必要な知見や技能を十分に持ち合わせて居ない場合に備え、適切な助言を与えることのできる人材を用意し公的資格を与える必要がある。
現行の「放射線取扱主任者」の制度を発展的に変更してこれに充てるのは望ましい選択となる。
- 空間の安全性確保の方策としては、「秒線量」が 1μSvを超えたときには(平時と異なる事態が発生したものと見做し)何らかの行動をとることとして“警戒信号”を発し、その前段階として「秒線量」が
0.1μSvを超えたときに、行動をとるための準備時間を与えるための“警戒信号”を発するのが、14までの記述とも整合の取れる、合理的方策と考える。
以上に述べてきた見解の根拠は、放射線安全科学に関わる仕事を、半世紀以上に亘って生業として来たことで身に付けた知見を背景に生み出された直観である。
この国では、法治と国際協調に価値を置き、それを国家運営の指導原理としていることもあり、関係法令に織り込まれた“線量限度”というものは、“ビタ一文超えてはならないもの”と受け止められ、現場では、その
7掛や 8掛を、実際の管理目標としていることが多い。 そのため、被曝監視を受けている者が実際に受けた被曝線量評価の結果は、扱いが別枠で決められている医療業界を別とすれば、その平均値や中央値が法の定める限度の
1/3~ 1/7まで低下する、というのが、これまで半世紀超える実績の結果である。
また、海洋には放射性廃棄物を投棄しないとしたロンドン条約に加盟した手前、被災した福島原発事故の収拾に際して発生した放射性排水についても適用されるべきものとしてきた。
しかしこれも、果たして、対象を拡大解釈し、条約の適応ありと判断したことが、当を得たものなのであろうかと考える。 非平和利用をも含めた世界の原子力大国には、原子力空母や原子力潜水艦を持つものも少なくないが、それらの船舶のすべてで、放射性排水を母港に持ち帰って居りとは信じがたい。
条約の締結に関わったI先生が『一生の不覚であった』と呟いておられたのを思い出す。 また、当時外務省の担当課長として同じくそれに関わった K氏は「海の岸から改定に向けてトンネルを掘り、そこの所蔵施設をつくって“保管廃棄”すればいい」と発言されているが、“あまりにも小細工”という感じが否めない。
参考までに書き加えることだが、ホルメシス論の推奨者として名高い近藤宗平先生(故人・大阪大学名誉教授)は、英国放射線科医の生涯被曝線量と死亡率のデータなどから、年間
30mSv、生涯累積線量 600mSvを安全限度に推奨したといわれており、同じく大阪大学医学部の中村仁信名誉教授は、一般人に対する安全限度に
500mSvを提案していると聞く。 因みに、筆者が生涯に受けた被曝線量を 10年程前に推定した結果は、職業被曝、医療被曝、環境被曝のすべてを併せると、実効線量にして
600mSvを超えるものであった。
ISS(国際宇宙ステーション)では、乗組員が、1日に 1~2mSvの実効線量を浴びているという事実にも目を留めて欲しいと願って居る。
<了>
rev 2016/06/17
|
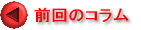 |
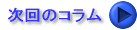 |
|
 |
|

